
Pitch a tent(テントを張る)
strike a tent(テントを取りはずす)という言葉からも、移動が伴うものと考えられます。
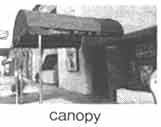
Canopy over the hotel entrance (ホテルの入り口の日除け)

| テントというと皆さんは何を思い浮かべるでしょう。運動会の時に使うテント、アウトドア用のキャンプテント、お店の前には装飾テント。チョット変わったところではトラックに掛ける荷台シートのことをテントと呼ぶ方もいらっしゃいます。このようにテントという言葉は非常に便利な言葉として、逆に言えば オールマイティな言葉として用いられております。それでは、そもそもテントとは何をさしているのでしょうか。荷台のシートがなぜテントと呼ばれるのでしょうか。お店の前につけるものが何故テントなのでしょうか。本当の名称はこれでいいの・・・?。ここでは、わたしたちが安易に使っているテントとは何か、そしてどのように言うのが本当なのか、私なりの解釈で書いてみたいと思います。あくまでも私の解釈ですので、間違いがありましたら指摘していただきたいと思います。 そもそもテントとは、移動用の簡単な住居のことをさしていたのでしょう。すなわち内モンゴルの遊牧民や砂漠を移動するベドウインやペルシャの人たちの住居を指していたと思われます。かれらの生活は移動を前提としているため木で骨を組み、その周りに獣皮や織物でふさいだものでした。中世になりを宗教という名のもとに(例えば十字軍の遠征など)侵略と破壊を繰り返したヨーロッパでは、軍隊用の移動用住居として発達していったと思われます。文献をあさったわけではないのではっきりしたことは言えませんが、当時使われていたテントの材質が船のセイル(英語でCANVAS)として使われていた丈夫な綿(麻)キャンバスではなかったのでしょうか。 CANVASを英語辞典でみると、 Sail,帆布とあり、使い方として、under canvas (軍隊が野営中) とあります。このことからも遠い古い時代には、船のセイルと軍隊用の移動テントとは密接な関係があったと言うことでしょう。 日本でも日露戦争以降海外に侵略した経緯がありますが、そのときの住居も野営用テントだったことは想像にかたくありません。その綿(麻)帆布を用いて野営テントを作る人たちをテント屋さんと呼んだのではないでしょうか。そのテント屋さんがシートを作り始めた。または、そこから出発して日除けを作り始めたので、テント屋さんで作るものすべてをテントと称したのではないかと思います。私の父は靴職人でした。三角針で革を縫い合わせる職人だったのです。その後靴から鞍へと移行し、昭和28年にシートの分野し進出し、3年あとの31年に日除けをやり始めたと聞いています。その父は、名前ではなく「テント屋さん」と呼ばれておりましたし、その父が作るものをお客様はすべて「テント」と称されたのではないかと思います。殆どのテント屋さんはそんな具合ではなかったかと思います。 |
| ひまにまかせて久しぶりに英語辞書でテントに関係するものを調べてみました。 |
| NAME | 辞書の訳 | 辞書の中で使われている写真 | 辞書の訳と写真から 私なりの解説 |
| 1)Marquee | 劇場などの出入り口の上に突き出たひさし。雨おおい、ガラス張り屋根。園遊会の大天幕。 |  |
プリティウーマンの映画のなかでポロの試合をした場面やロイヤルセブンティーンの結婚式のシーンニ出てきた大型のテントのことでしょう。 |
| 2)Tent | 野外用天幕。 | ・・・・・・・・写真ナシ・・・・・・・・・ | 軍事用テントやアウトドア用テントのことでしょう。 Pitch a tent(テントを張る) strike a tent(テントを取りはずす)という言葉からも、移動が伴うものと考えられます。 |
| 3)Canopy | 天蓋型のテント。自動車やボートのホロ。 | 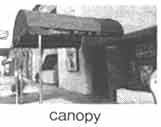 |
上から覆うようなテント。ホテルの入口に突き出たテントがありますがそのようなテントだと思います。 Canopy over the hotel entrance (ホテルの入り口の日除け) |
| 4)Awning | 窓・ポーチなどの日除け・雨覆い。 |  |
一般的な日除けテント・装飾テントのことでしょう。 |
| 5)Pavilion | 展示場にもちいる大型のテント。 | ・・・・・・・写真ナシ・・・・・・・・・・ | 博覧会場に使われます。 |
 |
 |
| マーキーの例(明治商工さんのロスベルガーのカタログより) | テントの例 (ウエンバーウォール型) |
 |
 |
| キャノピーの例 | パビリオンの例 |
他にももっとあるかもしれませんが、ボンクラ頭の私にはこれしか調べられませんでした。(百科事典でも調べたのですが「オーニング」という項目もありませんでした。)
これからみてもわかるとおもいますが、最近私達の耳になじんできている「オーニング」という言葉は,実際には可動式テントのことだけではなく、私達が言うところの装飾テント・日除けテントということになります。
では、欧米のかたは、どのように言っているのでしょうか。はからずも私が住む八戸は、米軍基地のある三沢市に近いということもあり、アメリカ人が多いので聞いてみました。
(実は私どもの子供たちが習っている英会話の先生がそちらの方なので、子供の送り迎えのときに勇気をふるって英語で話してみました。隣には、通訳さんもいましたけどネ)
おもむろに、写真集 [世界のテント VOL1] を開きながら 「これオーニング、これもオーニング」 と「オーニング」の連続でした。
そこでわかったことをまとめてみました。(本来なら、このようなことは個人の主観を排するため、何人もの方に聞いてまとめなければならないと思いますが、一人のアメリカ人が言ったこととして認識してください)
| 1) | 日本の辞書ではキャノピーとオーニングを区別していましたが、アメリカの方は同義語としている。可動式も固定式も同じオーニング。(キャノピーはあまりつかわない。) |
| 2) | ドームとは、半球形の屋根、または、形のことをいうので、われわれがつかうドームのことは 「DomeTent」 と言っている。 |
| 3) |
パビリオンとは、特殊な構造の建築物のことであり、construction(建築物)という言葉をつかっていました。ただ、そのアメリカ人は、建築関係に携わった方ではないので、本来のconstructionと仮設の建物の区別がつかないという可能性もあります。 |
ところが、日本では、「オーニング」といえば、バーネ型、又はコーベル型の可動式テントに限定されているのが現状です。日本オーニング協会のホームページをひらいても
―――――――― オーニングは、英語で「日除け」「雨よけ」という意味です。テント布地を巻取りパイプに取りつけ、季節や天候に合わせて出し入れし陽射しを自由にコントロールします。 ―――――――― 略 ――――――――――
そして、オーニングのいろいろと題して次の6種類をあげています。
| ロールタイプ(ボックスタイプを含む) | 一般的なバーネタイプの可動式テントのことです。 |
| ウインドウタイプ | 従来の(魚屋さんや八百屋さん等に使われていた)巻取りタイプのテントと考えてよいでしょう。 |
| フレキシブルタイプ | 窓の上からキャンバスを垂直におろし、任意のところでアームが前に倒れるタイプです。北欧でよく使われております。 |
| フードタイプ | コーベル型のオーニングと言ったほうがわかりやすいと思います。 |
| コンサバトリータイプ | サンルーム等の両サイドに設けたガイドに添ってキャンバスを伸縮させるものです |
| スクリーンタイプ | 外付けのロールスクリーンと考えてよいでしょう。 |
いずれを見ても可動式であることには変わりありません。一般的な装飾テントのことは一言も触れておりません。これはいったいどういうことでしょう。
実は、この「オーニング」という言葉をみつけてきたのが可動式オーニングのメーカーさんたちであったということ。そして、従来の日除けテントと差別化するために、「テント」いう言葉より「オーニング」という人知れない言葉を使った方がインパクトがあると考えたからでしょう。そして、可動式メーカーさんたちで(可動式だけの)日本オーニング協会なるものをつくったのです。
インターネットで「オーニング」を検索してみました。ヤフーでは41件、msnでは9966件の登録がありましたが、全部を見るわけにはいきません。両方とも20件ぐらいひらいてみたのですが、1件を除いて「オーニング」 イコール 「可動式テント」 となっておりました。例外の1件のテント屋さんも、「今では可動式テントのことです。」といった具合です。
「オーニング」という言葉も、少しづつお客様から認識され始めています。新築の住宅に「オーニング」を掛けたいんですが・・・というお電話の内容から、バーネのことだな・・・と察しはつきますが、逆にこのままでいいのかな???と思ってしまいます。
もしアメリカの方からオーニングの相談をされたとき、あなたはバーネのカタログだけを出して生地の種類を決めようとするでしょう。先方さんがもっと円形なものと言ったら、あなたはコーベル型のカタログを出して説明しようとするでしょう。えんえんと時間だけが過ぎ去り、結局はこの話なかったことに・・・なんていう笑い話も現実のものとなっていくかもしれません。
「日本オーニング協会」と銘打っているのであれば、固定式・可動式を問わず、オーニング全体のことを推進する機関デアルベキなはずです。
日本における装飾テント類のうちバーネやコーベルといった可動式の比率は何%あるのでしょうか。急速にその比率を伸ばしているとはいえ、まだ固定式のテントの方が圧倒的に多いはずです。それなのに可動式テントこそがオーニングで、それ以外はテントなのだという決め付け方はいかがなものか、はなはだ疑問が残ります。まるで、日本海軍がミッドウエー海戦での撤退を、「転進」という言葉で日本国民をだましつづけたことに似ていると感じるのは私だけ・・・ですね。ごめんちゃい。
でも、時代は少しづつ変化しています。オーニングという言葉が日本に入ってきた当時の事情を知っている我々ならともかく、次の世代になった時に、間違った意味の言葉をいつまでも使っていたのでは、”やっぱりテント屋だな” とさげすまされた見方をされることでしょう。
”さすがテント業界”といわれるためには、大所高所の見地から現在の日本オーニング協会は別な名前にして、誤解を避けるような行動をしなければならないと思います。
![]()